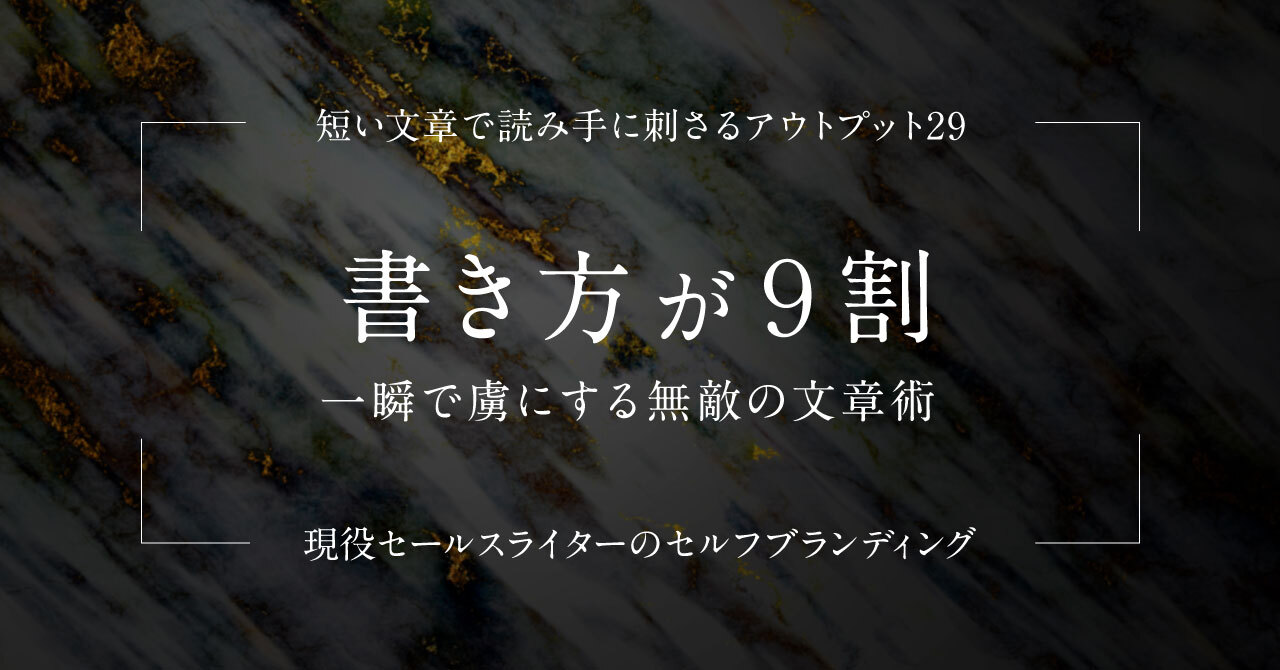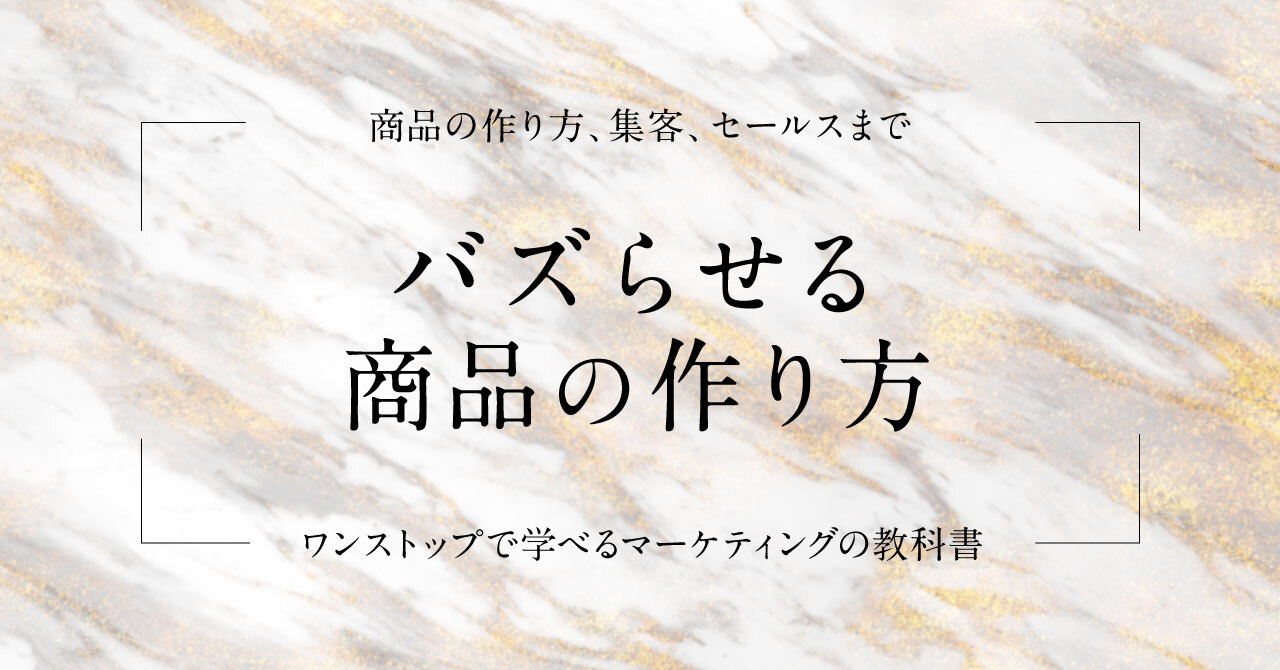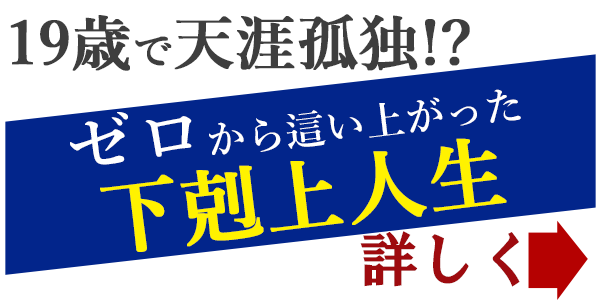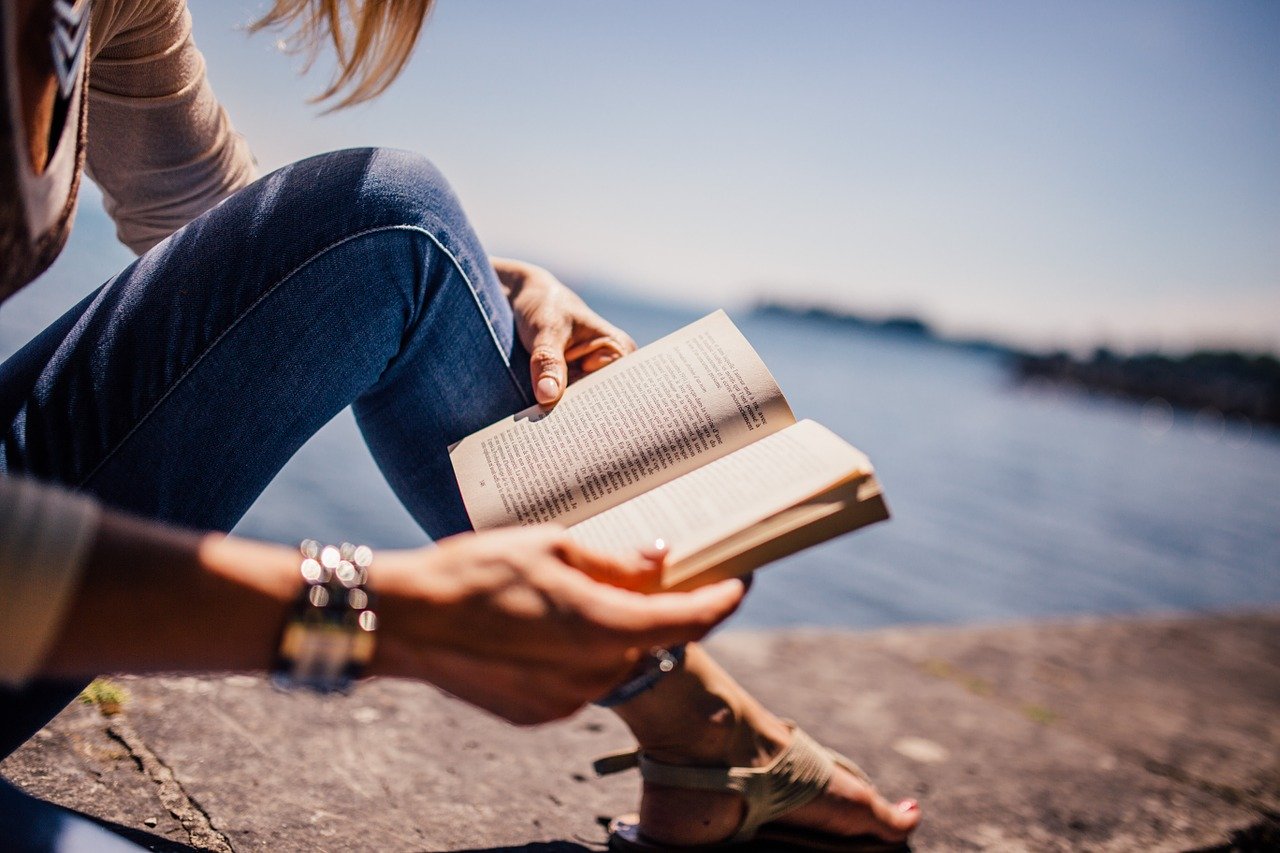
「あんなに言ったのに分からないなんて、部下の頭がおかしい」
「とても扱いが難しい部下の指導は、気を遣ってしまう」
管理者になった瞬間に聞こえてくる声である。
「こんなに部下の指導が難しいなんて思っていなかった」と声を漏らす人が多数。これは真実に目を背けた人間が発するコトバである。
まず「部下の指導が難しいと感じるのは、ただ単にあなたの力量不足に他ならない」という事実を直視するところからスタートすべきである。
私もその事実に目を背けずにいたところからスタートした。
本章では私の実体験を元にした、管理者なら外せない難しい部下の指導方法についてお話していきたい。
本章を読み終わった時には、考え方が他責から自責に変わり、部下への接し方が一変するだろう。
たった今から、部下に頼られるリーダーになろう。
部下への指導を難しいと感じさせる正体とは?

正体は、難しい説明をする上司本人だった
部下への指導を難しいと感じさせる正体とは、語彙力の低さに問題がある。
「あんなに言ったのに分からないなんて、部下の頭がおかしい」と言うかも知れないが、部下は「何回聞いても説明が理解できない」と思っているかも知れない。
自分が理解できるワードを部下にぶつけても、部下が理解できるとは限らない。
つまり「部下が分かるように話せていないのが根本の原因」なのだ。
部下の指導が難しいのではなく、自身の指導が難しさを招いている事実に気付くところから始めなければならない。
部下が難しいと感じる指導こそ、悪循環を生むのだ。
部下の指導は他責ではなく、自責である
私は29歳で会社役員に抜擢され、部下の95%以上が年上の先輩達だった。
誰も私の言う言葉など耳を傾けない。
そこで「私の言う話に聞く耳を持たないなら、部下が振り向く言葉を投げかければいいのか!」と思い、部下目線で話すようにした。
つまり自分目線ではなく、相手目線でものを考えるようにしたのだ。
例えば、野球経験者ならば野球を用いて部下に説明する。
私:「部署が違うからって、激しく争って良いわけではないです。争う気持ちは大事ですが、私達は仲間です。」
部下:「はい」
私:「野球の試合もそうだと思います。自分の強さだけを証明するのに、ファーストベースにいる仲間に剛速球は投げないですよね!?」
部下:「確かにそうですよね。周囲に対して敵対視し過ぎていました。ライバルでも仲間ですよね!」
このように、相手の身近なものに例えて伝えるのも1つである。
難しい顔をされたら、100通りの指導をする
部下の苦手分野を依頼すると、難しい顔をしながら返答される。
その度に「言う通りにならない部下の指導って難しいな」と感じていた。
相手に合わせた例え話を繰り広げても1回は言う通りになるが、また同じ本質のミスを繰り返してしまう。
1回言っても分からない人には、100回説明する気持ちで臨まなければ改善はされない。
根本的な問題を部下が理解できたとしても、行動に移せるかはまた別問題なのだ。
野球のスイングの理論は理解できたが、体が思うように動かない感覚に似ている。
だからこそ管理職の人間は、部下に100通りの指導をした上で改善する行動を起こしてもらわなければならないのだ。
部下の指導で得られる最大の恩恵とは?
難しい顔をする部下がいればいるほど、あなたの説明力に磨きがかかる。
『難しい顔をする部下が5人×100通りの教え方=500通り』
つまり部下の人数が増えるほどに「説得話法の引き出しが爆増する」のだ。
この技術は対部下でも大いに力を発揮するが、対業者にもエンドユーザーにも絶大な力を発揮する。
万が一、リーダーが説明力を放棄した場合、陰で「アイツの説明、わかりにくいんだよな」と部下に言われてしまう始末だ。
自分自身の仕事の出来高と、難しい部下を育てる能力は、似て非になるものである。
部下の指導をきちんと理解した上で、上司自身も邁進してほしい。
リーダーは部下に育てられるのだ。
「100通り伝えたのに、全く変わらない」という場合
その場合に限っては、見限っていい。
断言するが、これ以上部下に手をかけたとしても、改善されることはない。
原因は2つある。
1つ目は部下が今いる職業に合っていない場合。
もう1つは、尊敬されていない場合だ。
かなりキツイ言い方に聞こえるかも知れないが、事実である。
1つ目は、誰が何かできるわけでもない。
カナヅチな人に水泳を泳がせようとしても、泳げない。
無理に泳がそうとするなら、もはや虐待に近い。
2つ目は、お互いの精神面が削れていく上、お互いが不幸になってしまうので、「尊敬されていない?」と感じた瞬間に手を引くべきである。
尊敬されていないことに気付き、尊敬されるように頑張ったところで意味がない。
その頑張りは尊敬とは真逆の方向に進み、より一層離れていくからだ。
こればかりは「誰が悪いという話ではなく、ただ単純に生理的に合わなかっただけ」である。
バッサリ諦める手段も1つである。
100通り教える前に部下の特徴を押さえよう

指導には欠かせない部下の特徴分析!
人間には大きな括りで2種類に分けられる。
・私タイプ
・私達タイプ
部下をこの2種類のタイプ別に分けて指導してみてほしい。
私タイプ~基本的には自分で決定したい人間を指す。
職人気質が高いため、周囲の情報や意見を取り入れるのが苦手である。
職業で言うと、経営者や技術職の人に多い。
好きなペットは、猫が好きな傾向にある。
つまり「自由気ままに自分で意思決定をしたいタイプ」である。
私達タイプ~基本的には他人の意見や情報を意思決定の中心とする人間を指す。
奉仕気質が高いため、周囲との温度を合わせるのが得意である。
職業で言うと、営業やナースの人に多い。
好きなペットは、犬が好きな傾向にある。
つまり「協調性を持ち、周囲の顔色を伺いながら意思決定するタイプ」である。
部下を大きく2種類に分けたあとは簡単だ。
「部下の指導が難しい!」というのは、相手の性格を度外視して指導しているからであり、部下の性格を理解した上での指導は思いのほか簡単である。
もう「指導が難しい!」なんて言わせない!
・私タイプ
・私達タイプ
先ほど2種類に大きく分類した。
部下を「私タイプ」と「私達タイプ」で分けようと話したが、具体的な指導方法について触れていく。
例えば「私タイプ」の人間に指導する場合。
失敗時の指導:「君でもこんな失敗するんだね」
成功時の指導:「君じゃなければ、成功しなかったよ」
仕事の依頼:「誰もやったことないプロジェクトだからこそ、君に任せたいんだ!」
「私達タイプ」の人間に指導する場合。
失敗時の指導:「皆が失敗する箇所だから、次から気を付けてね」
成功時の指導:「見事周囲の力を引き出して、達成してくれたね」
仕事の依頼:「皆が君にこのプロジェクトをやって欲しいって言っているんだ!」
このように「部下のタイプに合わせて、話し方を変えてあげるのが本当の部下の指導」である。
これで「部下の指導が難しい!」という悩みから少し解放されると思う。
この技術と組み合わせて欲しいのが、次の”独自の読書術”である。
【必見】難しい部下の指導が簡単になる読書法

これで難しい部下もハッピーになれる読書術
難しい部下を指導するくらいなのだから、マネジメントの本などを読んでいるだろう。そもそも本気で部下の指導に悩んでいなければ、本章をここまで読んですらいないだろう。
だからこそ本気であなたに伝えたい技がある。
本を読みながら、「ココの箇所はアイツに伝えられるな」という読み方をして欲しいのだ。
1冊の本をただ読み進めてしまうだけだと、読んでいる本人が知りたい事項しか頭に入ってこない。
この本の読み方は非常に効率が悪く、勿体ない。
「ここの項目はアイツに伝えよう」
「これは彼女にピッタリだな」
このような読書法をすると、”部下の人数分の知識”がインストールされるのだ。
私はこの手法に何度助けられたか、と思うほど。
その上、読んでいる本人自身の能力も驚くほど上がる。
ぜひ難しい顔をした部下を指導する際に使ってみて欲しい。
読書こそ難しい部下への最高の指導書
読書せずして部下の指導は成しえないと思っている。
もう少し詳しく言うと、「読書で知見を得ると、時間が圧縮される」のである。
例えば自力で1年かかって得た指導法が、1日で得られるのが読書の利点。
つまり読書とは難しい部下の指導の予習をする効果があるのだ。
読書の使い方とは、時間を圧縮する点にある。
なぜ難しい部下の指導が読書で圧縮されるのか
例えばあなたがギターを始めようとする。
バイオリンでも何でも良いのだが、「初めて挑戦する分野」を思い浮かべて欲しい。
独学でギターのコードをマスターしたのなら、あなたは天才に近い。
だがマスターするのに10年かかったとしよう。
もしギターのコードを本で確認出来ていたとしたら、1年もかからずにマスターできるだろう。
つまり先人が残した知恵の結晶を拝借することで、最短で目標まで辿り着けるのが読書である。
私は難しい部下の指導に迷った際は、書店に行って「今の自分に合う本」を選んで読んでいる。
PS:難しい部下の指導に挑戦する方へ

難しい顔をする部下に言葉のプレゼントを!
挑戦する後ろ姿は、自分自身で思うより多くの人に見られている。
必ず自身の成長は周囲の人間に伝わる。
成長段階だとしても、部下にアツい熱が伝わる。
せっかく上司になるキッカケを貰えたのだから、自己成長しよう。
読書で語彙力を磨き、素敵な言葉を部下にプレゼントしていこう。