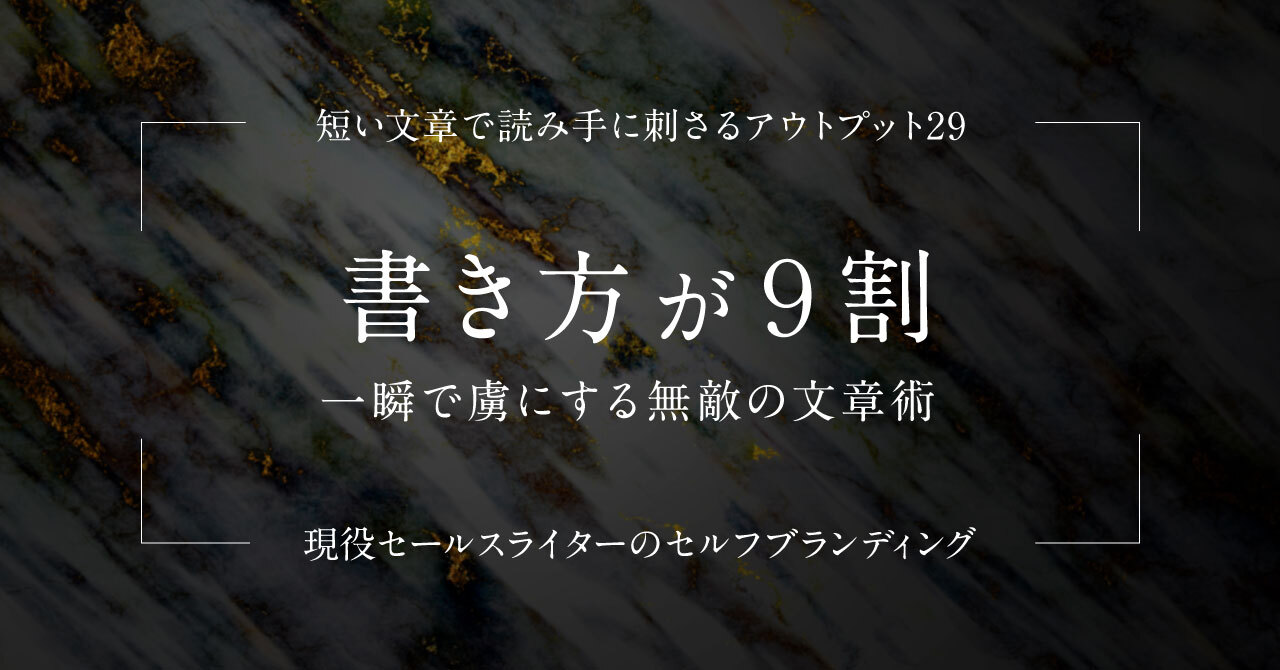せっかくのあなたの才能が、クセで帳消しになってしまう
無意識のクセほど、厄介である。
社内で「さっきまで○○さんと普通に話していたのに、何か不機嫌?」という状況はないだろうか。
ビジネスでいうと、「今回の商談は手ごたえあった!次が愉しみだ!」と意気込むが、連絡がつかなくなる。
こんな経験はないだろうか。
考えられる原因は、あなたの無意識の仕草や動作にあるのだ。
例えば、お客様が少しあなたが答えにくい質問をしてきたとしよう。
「10万、値引きしてくれたら買う!」と無理難題をお客様に吹っ掛けられたとしよう。
その際に、露骨に「なにいってんだよ、こいつ」と顔に出てしまった瞬間、ゲームオーバーである。
ただ、これは反応であり、無意識のクセではない。
無意識のクセとは、無理難題を押し付けられに際に、顔以外の細部に表れてくるのである。
「10万、値引きしてくれよ」と言われて、露骨に顔には出さなかったが、”あなたの持っているペン”に表れるのが無意識のクセである。
顔はニコニコしているのに、あなたの持っているペンが、”カチカチ、カチカチッ!”と、音を奏でていたとしたら相手はどう思うだろうか。
実際に私の部下のお客様からクレームの内容が、”ペンのカチカチ”だったのである。
そのお客様のクレームの内容は、「冗談で10万円値引いてくれたら嬉しいなぁ~」という気軽な気持ちで言ったのに、営業マンのペンが音を奏でたおかげで、イライラがお客様に伝わり、「何か本性が見えてしまって嫌いになった」という内容だった。
たった、ペンのカチカチ音が成約になるか否かの問題になるということだ。
もし、あなたが「イライラや苛立ちではなく、単なるクセだ!」と認識しているのならば、誤解される行動は即、やめたほうがいい。
実際に、どんなクセが相手を嫌がらせるか分からない。
分からないからこそ、極力クセをなくした方が良いのだ。
クセがなければないほど、お客様があなたに引っ掛かる嫌になる箇所の確率は下がる。
つまり、クセに足を引っ張られることなく、本来のあなたの実力が発揮されるのである。
どんなに素晴らしい説明を営業マンがしても、どこかのタイミングで、深いタメ息をしてしまったことで水の泡になる可能性もあるのだ。
ぜひ、クセを無くしてあなたの力を思う存分、発揮してお客様を笑顔にしてほしい。
余計な音や動作をなくせば、能力を発揮できる

案外、自分のクセというのは自分自身で分かっていないケースが多い。
これは他人に注意してもらうか、自分自身の行動を一つ一つ意識するほか改善策はない。
ただ、今この瞬間に「ペンのカチカチが嫌がる人もいるんだ!」と知るだけで、あなたはクセに対処できるはずである。
商談の時は、文字を走らせない限り”ペンを持たない”ようにすると決める。
電話対応で毎回、「いや、、大丈夫です!」の”いや”をつけないように気を付ける。
お客様との会話中に、”腕を組む”ことや、”テーブルで指をコツコツ”と叩かないようにする。
つまり、出来うる限り余計な動作や音をださないことである。
たったこれだけで、お客様の反応は劇的に変わるはずだ。
私が一次情報として体感しているので、間違いない。
私も余計な動作を排除してから、成績が急上昇したのである。
あなたも余計な動作に足を引っ張られている場合ではない。
一日も早く、本来の実力を発揮できるように励んでほしい。
PS:癖の改善と比例して、成績は挙がっていく

仕事がデキるのに社内で疎まれている管理職の男性がいた。
原因は、パソコンのエンターキーを「タンッタンッ!」と強く叩くことだった。
夜になればなるほど、周囲はそのエンターキー音に敏感になる。
本人に悪気などあるはずもない。
ただ、周りにいるスタッフは毎回その音が気になって、その度に集中力が途切れてしまう。
集中力が途切れる回数に従って、周囲は不快感を募らせていくのだ。
これは紛れもない事実である。
その後、私はその管理職の男性にエンターキーの”音”について話したところ、とても驚いていた。
エンターキーの音は静かな方だと思っていたのである。
やはりクセは、仕事に集中する瞬間に出るものであり、意識しないと直らないものである。
その指摘がキッカケで、管理職の男性が私に「今後、クセで何かあれば教えて欲しい」とのことだったので、気になる度に指摘させてもらった。
その結果、クセが直るたびに成績が比例して伸びていった。
どれも実話である。
追伸
私がクセを直すキッカケをくれたのは、社内の経理の女性である。
仲良くなって、こっそり私のクセを観てもらって、アドバイスを受けていた。
指摘を受ける度に、「女性の人を観る目には感嘆していた」のだった。
あなたも上司だけでなく、経理の女性、掃除のおばちゃん、誰でもいい。
仲良くなって指摘してもらおう。
なぜなら、一番成長するキッカケをくれるのは、いつも同性からの指摘ではなく、感性が違う異性の指摘だ。