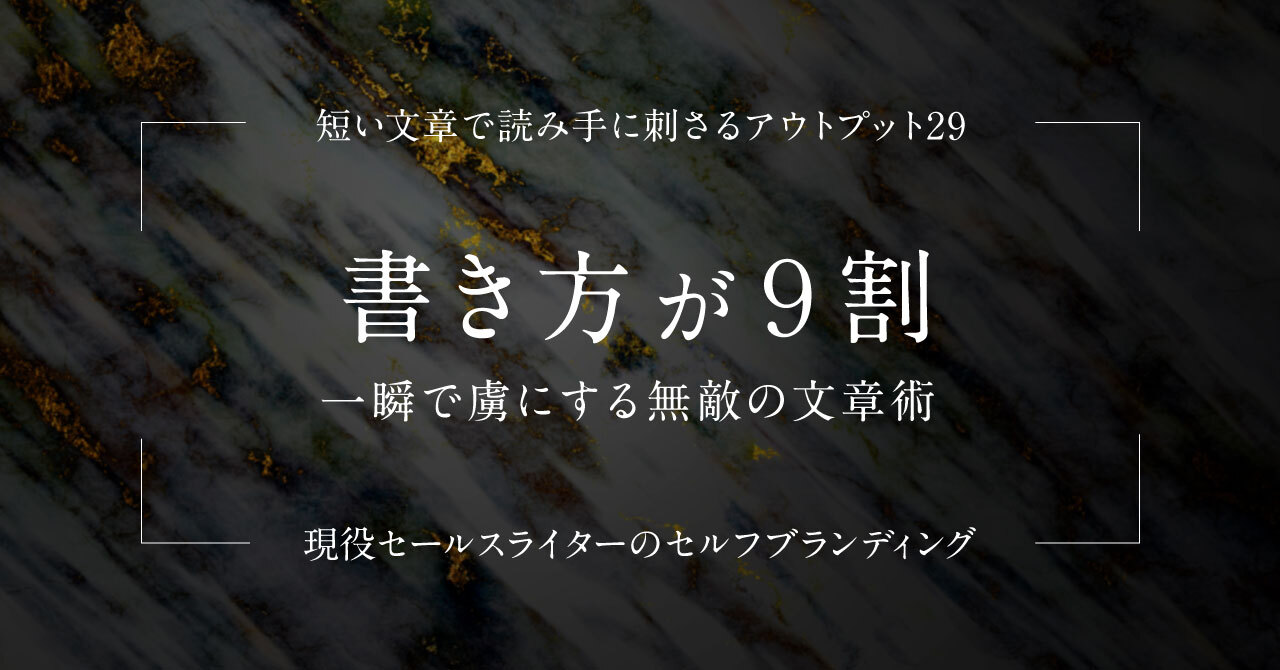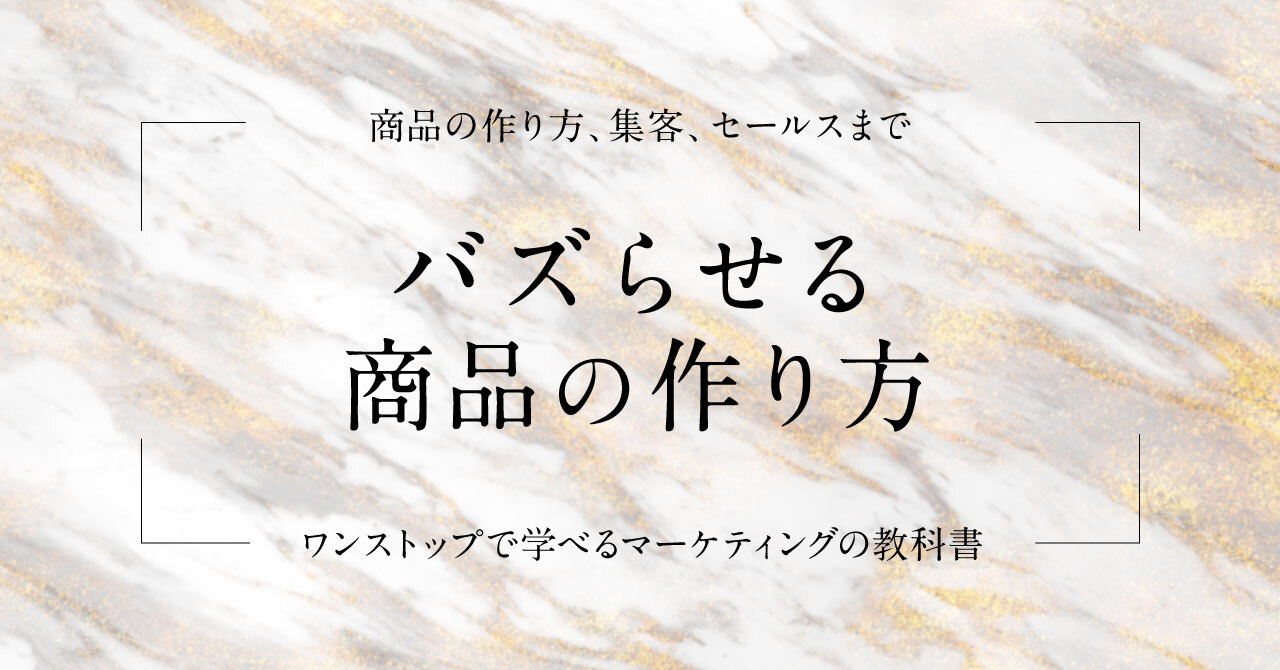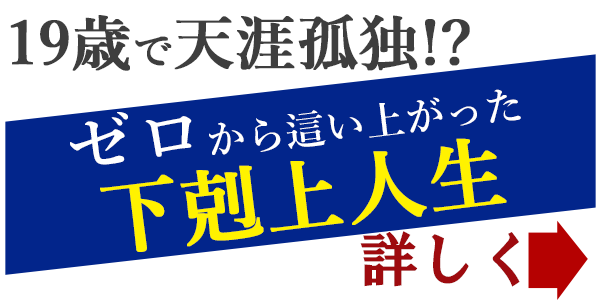Contents
今すぐ実践出来る11のコツ
商品を説明するだけの時代は終わった。
これだけ商品が溢れかえっている中で、他社との比較製品だけで購入してもらえる時代はもうこない。
商品の性能や価格に”差がない”となると、何が決め手になるのだろうか。
そう、あなたの営業力が決め手になるのである。
昔みたいなゴリゴリの営業は流行らないし、優越感に浸りながら知識を披露しても、お客様の情報量の方が多かったりする場合もある。
その上、お客様は気に入らないと思った担当者との縁を一瞬で切る覚悟がある。
なぜなら、あなた以外から好きな商品を買える手段が山ほどあるからだ。
もし接客する担当者が気に入らなかったら、隣の店舗に行けばいいだけである。
つまり、商品の性能や価格差がなくなると、お客様は人間を選ぶようになるのである。
お客様の心情は、「どうせ買うなら、気持ちよく買える人から買いたい」と心境が変化する。
だからこそ、”お客様との接客”で他社との差別化を図り、自社の商品を買っていただく確率をあげるべきなのである。
そこで、お客様との接客の際に気を付けるべき”11個のコツ”をご紹介する。
すぐに実践が出来る上に、長くたらたら文章を綴っていない。
サクッと読めて、サクッと使える技術ばかりである。
ぜひ、「今」から取り入れて実践で使って欲しい。
あなたの売上が180度変わることを楽しみにしている。
①お客様の事を”知る質問”を投げかけてみよう。
商品の説明やお客様の購買意欲を確認する作業より、まずはお客様のことをしっかり知る必要がある。
家を建てる営業マンを例にしてみよう。
「いくらがご予算ですか」
「土地はどこですか」
「間取りは決まっていますか」と。
これではお客様の事を”知る”のではなく、情報を聞き出しているに過ぎない。
「家を建てたいと思ったきっかけは何ですか?」
「家を建てたら、どういう暮らしをしたいですか?」
「その土地は思い入れがあるのですか?」
まず、あなたはお客様を”知る”ことから始めて欲しい。
一組、一組、商品を購入する理由は違う。
だからこそ、先に聞くべきなのである。
お客様を知ってからが、やっとスタートラインである。
信頼を得たあとは、自分から質問し続けなくてもよい。
勝手にお客様の方から話してくれる。
信頼関係を築く質問をすることによって、”あなたに興味があります”と相手に伝わるから信用が生まれる。
信用が生まれたあとに、初めて商品知識を披露することで”信頼”に繋がるのである。
ぜひ、試してもらいたい。
②話す順番は、説明からではなく結論から話そう。
話す順番を意識すること。
まず結論を、最初に持ってくるのだ。
話す内容が同じでも話す順番が違えば、伝わり方が何倍も変わる。
ビジネス社会で浸透している「起承転結」ではうまくいかない。
①結論
②理由
③具体例
結論は常にシンプルを心掛ける。
長い言い回しは必要ない。
お客様が「この家は光熱費かかりますか」という質問に、「この家は○○仕様で、尚且つ○○ヒーティングで」と言わないことである。
「この家は光熱費かかりますか」と聞かれたら、「12月の光熱費は〇〇円です。なぜならば~」と繋げる方が分かりやすい。
話す順番を変えるだけで、印象はガラリと変わる。
③常にポジティブな話し方をする。
ここでいうポジティブは、少し意味が違う。
希望を与える話し方の紹介である。
例)住民票がないと、土地決済が出来ません。
住民票があれば、土地決済出来ます。
意味は同じ事だが、伝わる印象は天と地の差がある。
例)13日の午後からしか、打合せ出来ません。
13日の午後からなら、打合せ出来ます。
比べると、違いに気が付くはずだ。
話す最後の語尾を”否定”ではなく、”肯定”で終えることで印象が180度変わる。
使いこなすだけで、一気に人を惹きつけることが出来る。
ぜひ、使いこなして貰いたい。
④惹きつける話し方はトーンとリズムが重要。
声のトーンとスピードを意識してください。
まったく同じ商品にも関わらず、売れる人と売れない人がいる。
話す内容が同じでも、「また話を聞きたい」と思われる方と思われない方がいる。
音楽で言えば、楽譜は同じでも奏でる人によって伝わり方が違うという事だ。
つまり声のトーン、リズム、スピードをどれだけ意識しているのか。
声のトーンを一つあげてみよう。
その上でお客様の話すスピードに合わせよう。
これが出来た上で、話と話しの”間”を空けずに話してみよう。
芸人さんのコントを見ると面白い。
テンポとスピードの使い方はプロである。
⑤お客様にメールを送る際には、一文一意が原則。
一文一意とは、一つの文章に一つの意味ということである。
お客様に熱弁すればするほど、一文が長くなる傾向になる。
とにかく簡潔に一文でまとめる事。
その上で、メールのやり取りも一文で簡潔を心掛けること。
メールなども一文が長いと、「あとで読もう!」と後回しにされる。
一文を短く、テンポよく、書くことで読みやすくなる。
お客様のメールの返信率も大幅に変わることだろう。
簡潔に、簡潔に、を心掛けよう。
⑥背中を押す、ひとこと。
お客様がどちらにするか悩んでいる時に、よく使うフレーズがある。
「個人的には、こちらが良いと思います。」
これはお客様の意思が、分かっている場合に使う、背中を押す言葉だ。
また、お客様の意向が分からない場合には、
「一般的に選ばれるのは、こちらです。」
しっかり悩ませてあげた上で、背中を押すことが大切である。
相手の意図が分かった上で、「私は、こっちが良いと思います」と、背中を押す一言を投げかけてみよう。
⑦余計なひと言を、いわない。
営業トークをじっくり観察すると、余計なひとことで損をしている。
商品によっては、高額商品を扱う職業もあるだろう。
高額な物を買えるということは、社会的地位が高いケースが多い。
もちろん、お客様の勤めている会社においては、トップ集団だ。
僕たちより社会的地位が高い場合も多い。
トップ集団の人たちに、蛇足を続けると、あっさり関係が途切れてしまう。
また、3代目経営者に多いのだが、話を聞き続けてくれる人がいる。
それにつられて、ペラペラ先生面で話していると、ジ・エンドだ。
余計なひと言をいわないことだ。
コツは、シンプルだ。
余計なことをベラベラ話すのではなく、”聞かれたことのみ、的確に答える”ことがコツである。
「今」から試してみよう。
⑧電話の語尾のトーンを下げない。
電話の取り方で、大きく損をしている方が多い。
顔が見えない相手だからこそ、声のトーンを意識しよう。
そして、ここが一番大事なところだが、
電話の終わり際にトーンが下がる。
それまでの電話対応が完璧でも、最後の最後の語尾のテンションで『素』が見えてしまう。
そこに「違和感」を覚える人もいる。
お客様は電話対応が気に入らないだけで、その商品は買わない。
会話を聞いていると、最初は明るいが、最後の語尾にかけてトーンが下がっている方が多い。
終わり際こそ、”元気よく”を心がけよう。
⑨本当のイエス・バット話法。
世間一般に言われているイエス・バット話法は、「そうですよね。ただ~です。」である。
肯定したのち、否定する方法が一般的である。
しかし、本当のイエス・バッド話法は、あなたが質問をして、”お客様自身に否定させる方法”だ。
例えば、トヨタのクラウンを買うお客様に「高いな」と、言われた場合。
【普通のイエス・バッド話法】
「そうですよね、ただトヨタでも高級車ですから、高いです。」
【本当のイエス・バッド話法】
「そうですよね。ただ、何と比べて高いとお考えでしょうか。」
ぜひ、使いこなして頂きたい。
驚くほど、効果があることに気づくはずだ。
私は何度もこの話法に助けられてきた。
⑩業界用語・専門用語を使用しない。
大部分のお客様は素人である。
当たり前の顔で、業界用語を使う人を、お客様は説明が分かりにくいと感じるはずだ。
遠回しに、お客様に対して「勉強不足ですよ」と伝えているようなものだ。
知的に話しているように感じるのは、本人だけ。
本当の知的な話し方は、小学生にも分かるように話すことだ。
慣れ親しんだ社内で使う言葉を、平気でお客様に話している。
「地役権があるため、制限がかかります。」
建築用語だが、理解出来るだろうか。
あなたも素人だった時に苦労したはずだ。
その苦労をお客様にもさせてはいけない。
ぜひ、「専門用語」を使わず、分かりやすい言葉で話してみてほしい。
お客様の目の色が変わる瞬間に、立ち会えるはずだ。
⑪あえて、天然なフリをする。
賢いふりをすると、相手は本音を言わない。
少し抜け感を出すと、相手の緊張が和らぎます。
”普段は完璧に仕事をこなすが、ドジな面も見せる”
そうすれば相手は気を許し、本音を言いやすい環境がつくれる。
実際に、お客様から何度も言われてたことがある。
「秀吉さんって、そういうドジな一面もあるんですね。安心しました。」と。
思わず、「安心とは何ですか」と聞き返した。
そうすると、「なんでも完璧にするから、私たちもミスしちゃいけないと思っていました」と。
これを聞いた時に、「知らずにプレッシャーを与えていたのだな」と思い、少し忘れ物をすることにした。
それからは、多くのお客様に「気軽になんでも話せる」と言われるようになった。
これも、実話である。
マメ過ぎる心配性のあなたも、ぜひ試してほしい。
PS:知っているだけだと、宝の持ち腐れである
「なんだそんなことか」と思った人もいるかも知れないが、知っていることと、出来ていることは違う。
大多数の人を観察すると、知っているが”やっていない”ことが多い。
”そこに”チャンスがある。
行動に移せない人が山ほどいるから、行動に移した人が目立つ。
どこの世界でも全く同じだと思う。
せっかく知識を得たのに使わないのは勿体ない。
ぜひあなたには知識を知恵に変えて、活躍して欲しい。